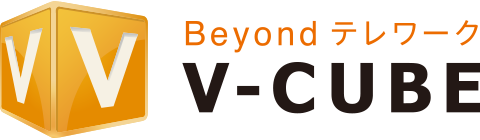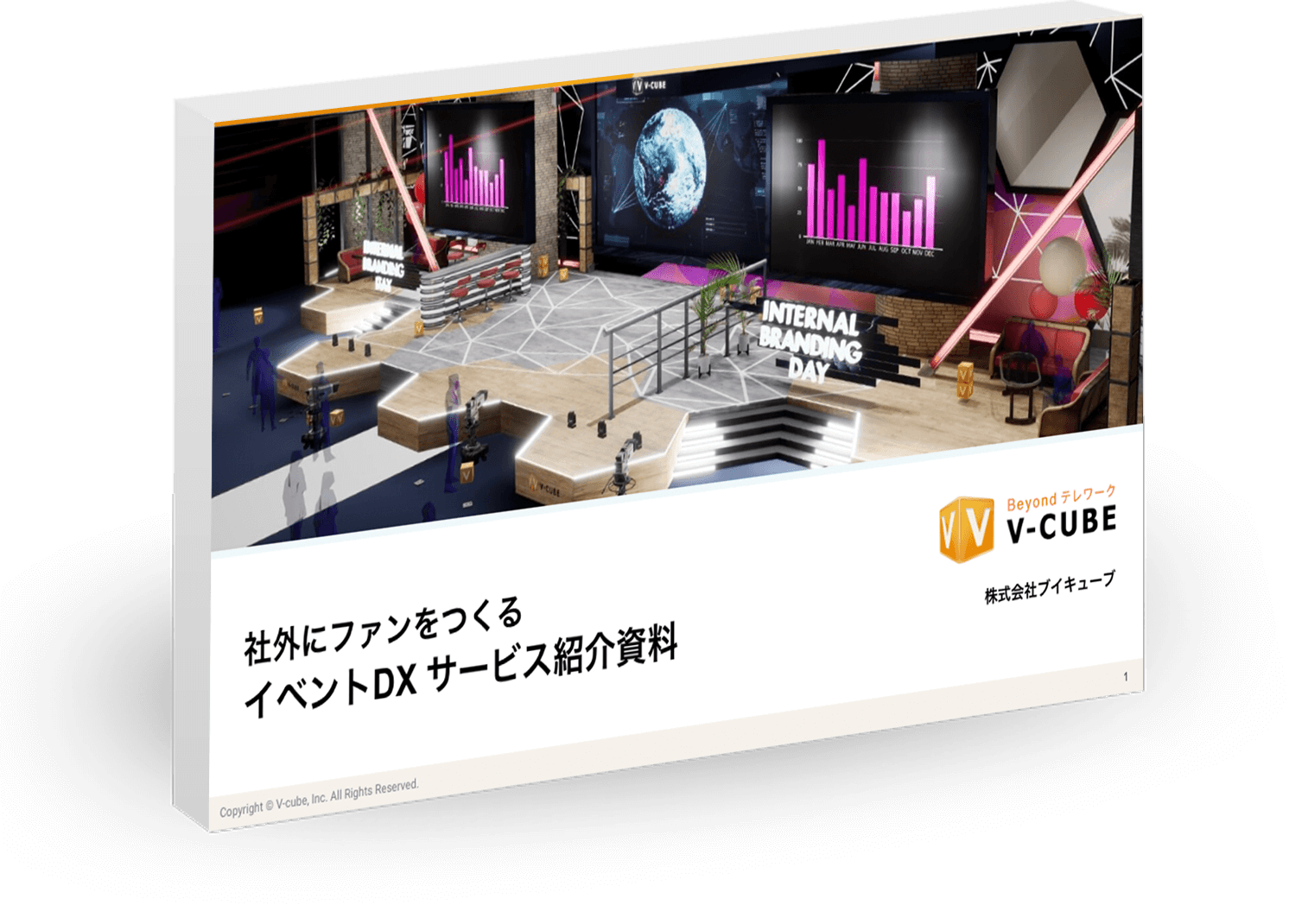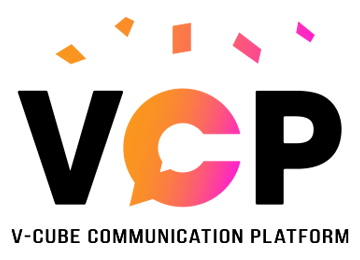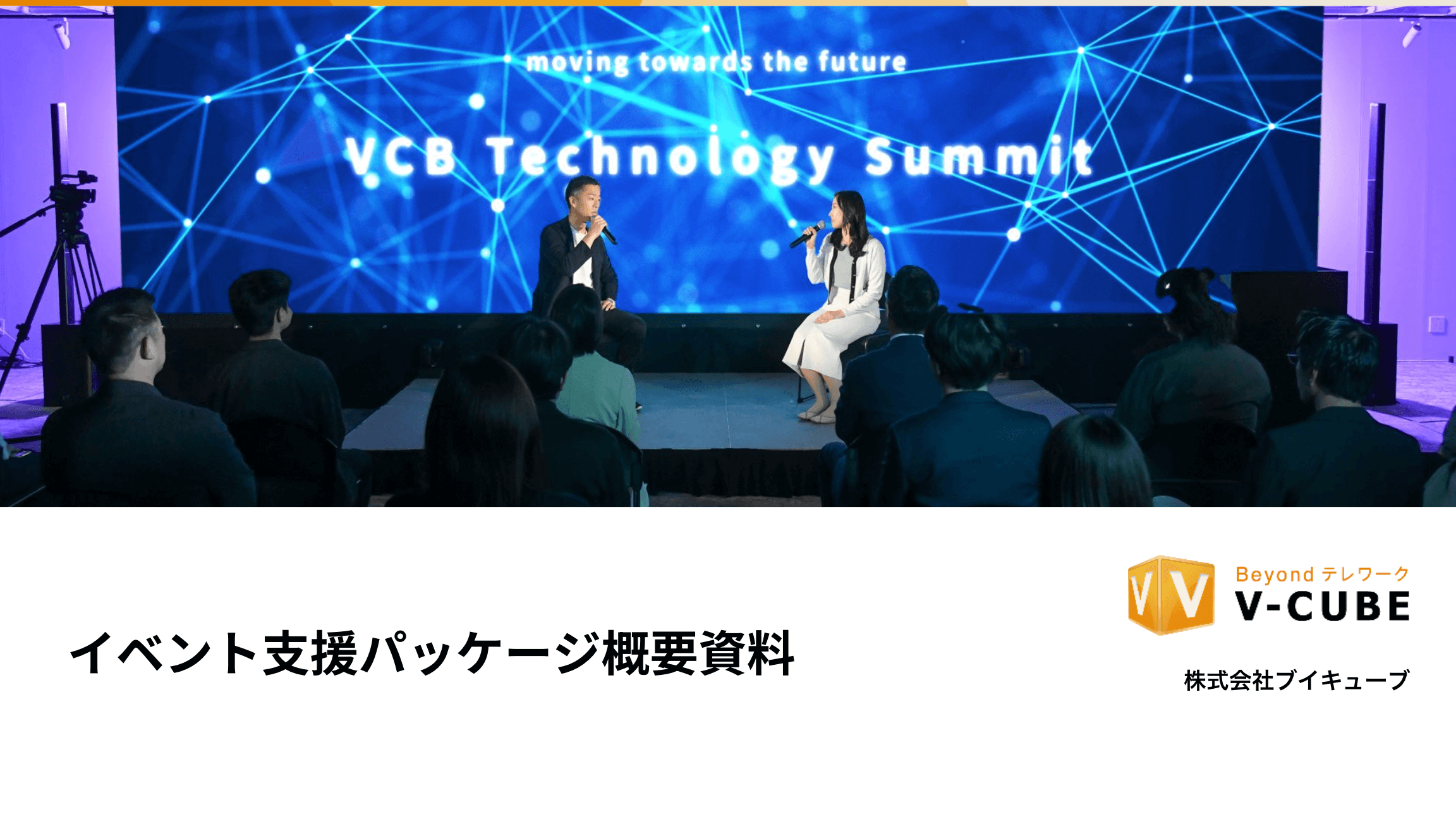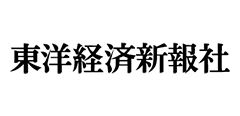企画から運営まで
成功へ導くイベント設計
記憶に残るイベントを創出!参加者の心を動かすイベントプランニング
「セミナーやカンファレンスが成功しない…」そんなお悩みはありませんか?
ブイキューブは、イベント企画・運営のノウハウとデータ分析で、
貴社のイベントを成功に導きます。
記憶に残る体験を提供すると共に、参加者の行動を可視化。
イベント後の成果にも繋げます。
企画から運営までを一貫してサポート。お気軽にご相談ください。

PLANNING
イベント企画
イベントもセミナーも成功へ導く!
企画・運営からログ分析まで、ワンストップで支援
イベントやセミナーの目標は、お客様によって様々です。参加者の満足度向上、ブランドイメージアップ、売上増加など、どんな目標でも達成できるよう、ブイキューブは全力でサポートします。
大規模セミナー、社内イベントなど、多様なイベントの企画・運営はもちろん、オンライン・対面問わず、柔軟に対応。
企画の一部分から、トータルな運営まで、ニーズに合わせて最適なサポートを提供します。
データ分析に基づいた戦略で、記憶に残る、そして成果につながるイベントを作り上げましょう。

販促・マーケティングイベント
製品・サービスの魅力を最大限に引き出す!
セミナー、カンファレンスなど、販促・マーケティングイベントの企画・運営をニーズに合わせて最適なサポートをご提供。ターゲット層への訴求力を高め、売上アップに繋げます。

社内イベント(社員総会・記念イベント等)
社員のモチベーションUPに!
周年・記念イベント、社員総会、入社式など、社内イベントの企画・運営で、従業員と会社の絆を深めます。活気あふれる職場づくりをサポートします。

医療・製薬・学術イベント
専門性の高いイベントを成功に導きます!
製薬業界におけるWeb講演会など、医薬・学術分野のイベント企画・運営で豊富な実績。規制対応も万全で、安心して開催できます。

バーチャル株主総会
場所や時間を超えて、株主とのコミュニケーションを深めます!
バーチャル株主総会をスムーズに開催。200社導入の信頼と実績で初めての開催でも安心のサポート体制です。

決算説明会
投資家との信頼関係を構築!
決算説明会をオンライン化。遠隔地の投資家にもリアルタイムで情報を届けます。配信スタジオ・ハイブリッド会場も完備しています。




映像技術・スタジオ
リアルタイム合成やVR・XRの技術でイベントの盛り上がりを演出
3DCGでのリアルタイム合成や、アバターで交流できるVR・XR技術など多彩な映像技術でイベントを盛り上げます。
オープニングムービーの制作や講演の事前収録も承っており、配信や収録ができるスタジオも完備しています。
詳しく見る
3DCG配信
圧倒的な演出力で、視覚に訴える次世代配信を実現!
リアルとバーチャルが融合した3DCG配信で、インパクトある演出が可能に。商品紹介やイベント演出を革新し、視聴者の心をつかみます。

事前収録・映像制作
伝えたいメッセージを、高クオリティな映像で表現!
プロフェッショナルによる高品質な映像制作で、事前収録から編集まで一貫対応。安心・確実な映像コンテンツが、イベントの成功を後押しします。

PLATINUM STUDIO
白金高輪の高品質オンラインイベント配信スタジオ
駅から徒歩5分!アクセス抜群のロケーションと、設備の整ったスタジオ環境。イベントの規模や目的に合わせてオンライン配信・収録に最適なスタジオをお選びいただけます。

ハイブリッドイベント会場
場所や環境を超えて、一体感を生み出すイベントを実現!
来場者とリモート参加者を同時に惹きつける演出と導線設計。現場運営から配信まで、ハイブリッド型の成功を徹底的にサポートします。

ROYAL STUDIO
大阪・梅田で、最先端の配信技術と自由度の高い空間演出を
最先端の配信設備とプロフェッショナルの映像技術チームが在籍する映像収録・配信特化型スタジオ。セミナー、展示会、ライブ配信など、幅広いイベントニーズに対応します。
イベント開催・分析システム
イベントの規模や目的に合わせて選べるオンライン配信システム。